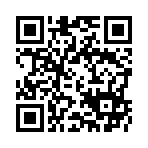2017年02月24日
■■ 人の声は素晴らしい楽器と言う話 ■■

まず始めに人間の声について話してみましょう、私の教室に始めて来られた方が最初に言われる言葉が「私は、声が悪いから」、「私はオンチだから」とほとんどの方が言われます。
そこで、この二つの悩みや疑問に始めに答えを出して、自信を持っていただきたいと思います。
結論から先に言います。
◆真性のオンチは殆どいません、リズムオンチも音程オンチも殆ど の方が治ります。
◆声が悪いからとお悩みの貴方、その声は貴方の「個性」なのです、 歌は声の善し悪しで唄うものでは有りません「こころ」で唄うものです。
さて、ひとが生まれて始めて声を出すとき、これを産声と言います、この産声の音程[たかさ]はどの赤ちゃんも殆ど変わらないと言われます、それは赤ちゃんが生まれてこの世で始めてする呼吸によって声帯が鳴る音で、生きる証であることは皆さんご存知です、この産声の高さが殆ど同じたかさだと言われます、それはは、赤ちゃんの声帯の長さがどの赤ちゃんも生まれてすぐには殆ど変わらず、声帯を支える筋肉が未発達のためだと言われます
赤ちゃんの声帯の長さは約6ミリだそうですが、成長して大人になっても8ミリから9ミリと言います、人はそんな小さな声帯を震わせて声を出し言葉を話しているわけです。
************************************************************
赤ちゃんの産声の高さはドレミで言うとハ長調の“ラ“の高さ近いそうです、イロハやABCで表記するとイロハノのイ、ABCのAとなります、不思議ですネ。
ちなみに ”ラ”の音は440ヘルツでピアノの鍵盤で、低いほうから4番目の”ラ”、A4になりますがこれは世界基準になっています。************************************************************
声帯はちょうど喉仏の奥に有り、気道の上の部分にあります。
そして、気道の奥に食道があり、気道の上部に気道蓋と呼ばれる蓋が有ります、これは気道に飲食物や唾など飲み込むときに気道から気管支や肺に異物が入らないように自律神経が働き呼吸のときや声を出している時以外は閉じるようになっています。
声帯の構造はちょっと乱暴なたとえですが、判りやすく言うと竹の筒を思い浮かべてください、竹筒の空間を仕切る節の部分が声帯です、そして節の中央にたてに切れ目があり左右一対のやわらかい襞の弁があります、この左右一対の弁の間に息を通して弁を振動させて音を作り出しています、また、この弁を支える周りの筋肉がありこの筋肉を緊張させたり弛緩させたりして音の高さを変えています。
声帯の音を作り出す原理はトランペットやトロンボーンなどの金管楽器と同じなのです、トランペットはふき口(マウスピース)に唇を当てて息を通して唇の振動で音を作り出します、トランペットのふき口をはずして吹いてみるとまるでオナラのようなビーと言う音がします、そんな殺伐な音がトランペットの管の中を通すことによってあの煌びやかで伸びやかなあんなに大きなトランペットの音となって出てきます。
それは、ふき口で作り出された殺伐な音が管の中を通るとき反響し、共鳴し音に丸みをつけ増幅してあの素晴らしい音となって生まれてきます。
人間の声も同じなのです、声帯で生まれた音は咽喉、口腔、そして鼻腔を通り口外に出るまでにトランペットと同じことをして声を作り出しています。
そうです、貴方自身が、貴方の個性有る素晴らしい声と、「ことば」という「こころ」を伝える素晴らしい道具を持った楽器なのです、そしてそれを演奏しうる名演奏家なのです。
人の声も十人十色と同じ声質の人はいません、それは主に人それぞれに骨格が違い口内の形状や肉づきなど複雑な要因からくるものです、親兄弟の声が似てくるのも遺伝と言ってしまえば簡単ですが骨格などの構造的なものが大きく影響していますから似てくるもので、声の質を変えることは難しいことです。
親から頂いた声ですもの、世の中でたった一つしかない貴方の声を大切にして自信を持って唄いましょうよ。
歌は唄うための声の良し悪しではありません、唄う歌の詩を心を込めて伝えることが大切ですよね。
ここで皆さんに注意していただきたいことがあります、それは、間違った発声法でむやみに声を出していては声帯をつぶしてしまうと言うことです、私の周りにもそのような方が沢山おられますが、きちんとした発声法を指導できる方はそう沢山いるとは思えません、発声法はきちんとしたボイストレーナーに指導を受けることをお勧めします。
Posted by 歌バカじいちゃん at
22:27
│Comments(0)
2017年02月24日
歌謡曲の歴史
■■ 歌謡曲の歴史 ■■
歌謡曲の歴史はそんなに古いものでは有りません、明治の後期に入りバイオリンを引きながら街角で唄う演歌師が現れ、歌詞を書いた小さな本を売っていたのが始まりと言われます。
そして、大正の初めに中山晋平作曲の「カチュウシャの唄」がはじめて日本国内で制作されてレコード発表されました、その後「かごの鳥」、「船頭小唄」など、中山晋平作曲の歌が世に出て、現在の歌謡曲の原型ができたと言われます。
その旋律は、それまで演歌師が唄っていた旋律とはまったく違った新しい旋律でした、しかし、そんな新しい旋律の中身は、洋楽の旋律と、三味線やお琴に代表される日本の旋律が交錯する、中山晋平の計算し尽くされた旋律に対する考え方と中山晋平自身の極めて日本人的な感覚が絡み合い、日本人の心をとらえて離さない素晴らしいメロディーが生まれたのだと思います。
しかし、船村徹先生は歌謡曲、演歌のルーツはご詠歌だと言われます、それは、リズムやメロディーを言われているのではなく、歌謡曲(演歌)を「日本人の心と言うならば」と考えての事ではないでしょうか。
私は、この話を聞くまでは自分の考えとして源氏物語など琵琶法師が歌い伝えたものが始まりではと考えていたのですが、船村先生の言われるようにもっと古く庶民の心を庶民自らが歌い継いだご詠歌が有ることに気がつかされたものです。
私の渋谷での演歌師の大先輩でもある北島三郎さんがこんなことを話しておられました、「フランスにはシャンソン、アメリカにはジャズ、イタリアにはカンツォーネ、そして日本には演歌が有る」と。
Posted by 歌バカじいちゃん at
01:53
│Comments(0)
2017年02月23日
はじめに・・・。

皆さん「カラオケ」、楽しんでいますか?・・・・・。
「カラオケ」は、いまや世界の共通語になっていますね、世界中でカラオケを楽しんでいる方が沢山います。
国内でもカラオケ喫茶やカラオケボックスも大型店舗が沢山出来ていますし、またカラオケサークルもたくさん出来て、NAK(日本アマチュア歌謡連盟)など、大きな組織も活動しています、いまやカラオケは国民的な娯楽になっていますね。
カラオケを楽しんでいる方も若い方からお年寄りまで歌のジャンルも幅広く楽しんで居られます。
何よりもカラオケがここまで国民的な娯楽となって来たのは、カセットテープや8トラックテープから始まったカラオケの音源は、脅威的な発展を遂げて音源のデータがアナログからデジタルになり、音楽は数字に変換されて保存、再生される様になりました、皆さんの一番身近なところでは、CD・MDなども数字として記録されています。
そして、シンセサイザーの音源がデジタル音源になるとカラオケも通信カラオケとなり飛躍的に発展してきました、またハードディスクの容量もテラバイトの世界になり、いまや小さなハードディスクの中に20万曲以上もの曲が収録される時代になっています。
■■ 演歌は、日本人の心! ■■
「演歌は、日本人の心!」、とよく言われます、裏を返せば「演歌は心で唄え」、と言うことではないでしょうか。
とかく周りの人達から「お上手ですね!」、と言われている方には、自分の声の良さや、唄うための技術を目いっぱいに前に出して、これでもか、これでもかと唄っている方が多いようです、歌は、全てに於いて余裕がなくては、いい歌は唄えません、発声の仕方、こぶしのつけ方、ブレスの取り方など、すべては余裕を持って唄うためのもので、その余裕が歌の情景や情感、そして言葉や語尾の余韻を生み、声に「色」を生み出してゆきます。
歌を唄うと言うことは、歌を聞いてくれる人がいる以上、自分だけが満足して気持ちよくなっていたのではいけませんね、どんな場合でも、貴方の歌を聞いてくれている人も、心の中で一緒に唄っていることを忘れずに聞いてくれている人達も心から楽しめる、そんな歌を唄いたいものです。
Posted by 歌バカじいちゃん at
22:03
│Comments(0)